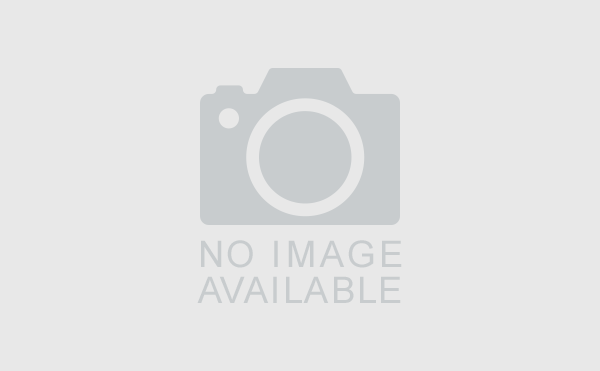下方修正された事業計画の不提出が表明保証違反とされた事例(東京地判R2.10.26)
本件は、Xが、自らが創業し代表を務めていた甲社の大部分を売却したY社に対して、株式譲渡代金の留保分の支払を求めたのに対し、Y社が表明保証違反を理由に支払を拒んだものです。
XY間の株式譲渡契約には、以下の条項がありました。
・株式譲渡金額:36億7920万円
・留保金:5億5188万円(補償請求がなければ支払う)
・補償条項(契約12条):Xが契約違反や表明保証違反をした場合、被告は損害を請求可能。
請求は1件500万円超であることが要件。
契約から1年半後、この留保金を巡って、Xが支払請求訴訟を提起したのが本件です。
表明保証違反の有無が問題となったのは、契約締結後に甲社が策定・承認した「本件事業計画」に関する情報開示の有無です。Yは、譲渡前に開示されていた「提出済事業計画」(旧事業計画)と比べて、本件事業計画は業績見通しが大幅に下方修正されており、それが開示されなかったことは重大な契約違反(表明保証違反)であると主張し、請求棄却を求めました。
本判決は、「企業買収の場面において、売主側の事業者が作成する事業計画は、DCF法による企業価値の算定に当たって必要な資料であるとしても、事業計画は、当時の事業の状況を前提とした予測の部分を含むものであり、買主側は、デューデリジェンス等を通じて当該事業計画の実現可能性を検討し、表明保証条項を通じてその基礎となる財務諸表等の正確性を担保するなどして、企業価値を算定しているのであるから、提示された事業計画と、その後の実績との間に差異があったとしても、その一事をもって表明保証条項に基づく補償請求をすることはできないものというべきである。
しかし、企業買収における企業価値の評価に当たっては、DCF法が用いられることが多く、現に、本件譲渡契約においても、原告又は本件対象会社のフィナンシャル・アドバイザーであった甲銀行が、提出済事業計画を基礎資料としてDCF法による簡易評価を作成し、これを売却先候補者に交付していること、Yが、譲渡を受けたいとの意向表明をするに当たっても、提出済事業計画の数値の信頼性が、評価価額を修正する要因となりうる旨が記載されていることからすれば、XとYは、提出済事業計画の数値が、本件対象会社の価値の算定において重要な要素になることを互いに理解していたものと認められる。
そして、本件譲渡契約上も、Xは、本件譲渡契約締結後譲渡日までの間、甲社に対して、キャッシュフロー又は将来の収益計画に悪影響を及ぼすおそれがある事由又は事象が生じた可能性を認識した場合には、直ちにYに対してその報告を行うものと定められていること・・・、さらには、Xによる表明保証条項においても『対象会社の事業の見通し及び収支計画につき、直近の財務諸表の作成基準日以降、譲渡日までの間に、本件株式の価値に悪影響を及ぼす事由は生じていない。』と定められていること・・・に照らせば、本件譲渡契約締結前に生じた事由であったとしても、Xが、契約締結時までに、Yに対し、そのような事由及び事象を開示しておらず、その内容が将来の収益計画に悪影響を及ぼしうる場合には、Xは、Yに対し、これを開示すべき義務を負うものと解すべきである。
そうすると、提出済事業計画の予測値が大幅に下方修正され、その修正が、何らかの事情の変更に基づくものであった場合には、それらの事情の変更が、将来の収益計画に悪影響を及ぼす事由又は事象に該当すると共に、本件譲渡契約・・・にいう『本件対象会社又は本件株式に関する情報』に該当するのはもちろん、事業計画を大幅に下方修正したとの事実自体についても、将来の事業計画に悪影響を及ぼす事由又は事象を認識しうる端緒であるといえるから、『本件対象会社又は本件株式に関する情報』に該当しうるものと解すべきである。」
つまり、本件事業計画の策定により見込まれる営業利益・経常利益の大幅な減少は、企業価値の算定に重大な影響を与えるものであり、これを被告に開示しなかったことは表明保証条項違反に該当するとしました。
さらに、補償金額の算定にあたって、「被告が、原告に対し、補償請求できる損害は、DCF法によって、提出済事業計画を用いた場合に算出される企業価値と、本件事業計画を用いた場合に算出される企業価値との差額を基本として算定することが相当である」としています。
結論としては、Yによる補償請求が正当と認められ、留保金を支払う義務はないと判断され、Xの請求は棄却されました。
本件から得られる実務上の重要なポイントは以下のとおりです。
- M&A契約における表明保証をどのように定めるかは非常に重要である。「事実」のみならず、将来の予測(事業計画)についても表明保証の対象とするのであれば、その内容や範囲を明確に定めておくことが事後の紛争を予防する。
- 非上場企業の株式価値の算定にあたってDCF法が用いられる場合、事業計画の変更は企業価値に直結するため、その変更内容の開示義務は重要である。
本件は、契約の具体的条項とM&A実務に即して、開示義務の範囲が詳細に検討されています。今更ながら、M&Aにおける譲渡契約書の重要性を痛感する裁判例です。こういうところが法律の面白いところであり、難しいところです。
さらに詳しく知りたい!→M&A契約の表明保証について詳しく確認したい方はこちらのサイトをご参照ください。